こんにちは、アラカンぼっちトラベラーのヴィオラです。
特に「便利そうだけど、なんとなく怖い」と感じているシニア世代の方が、
AIを日常の味方として少しずつ取り入れられるように。
AIについてほとんど知らなかった私、ヴィオラが実際に使い始めた経験をもとに、
漠然とした不安をやわらげ、安心して活用するためのヒントをお伝えします。
今回は長い記事になりましたが、どうか最後までお付き合いいただき、
さらに豊かなシニアライフを私と一緒に目指しましょう!
AIは「魔法の道具」ではない
最近よく耳にするようになった「ChatGPT」や「生成AI」、
「スマートスピーカー」など、
テレビや新聞でも話題になっていますよね。
なんだか便利そうだけど、時代に置いていかれそうな気もして、ちょっと気になる・・・
でも、「AIって難しそう」「なんとなく怖い」と感じて、つい敬遠してしまう。
そんなふうに思っていませんか?
でも大丈夫。
まずお伝えしたいのは、AIはあくまでも“道具”だということなんです。
たとえば包丁も、料理に欠かせない便利な道具ですが、
使い方を間違えればケガのもと。
それと同じで、AIも「どう使うか」「どう向き合うか」で、
頼れる味方にも、ちょっとした落とし穴にもなるんです。
無料だからといって安心しない
多くのAIサービスは、基本的に無料で使えるものが多く、
スマホやパソコンがあればすぐに始められます。
「えっ、無料なの?それならちょっと試してみようかな」と思ったあなた。
はい、それはとても良い一歩です。
でも・・・ちょっと待ってください。
実はここに、小さな“落とし穴”があるんです。
たとえば、多くのAIサービスでは、無料で使える代わりに、
「あなたが入力した文章や画像を、AIの性能向上のために使います」と
利用規約に書かれていることが多いのです。
つまりどういうことかというと・・・
あなたが何気なく入力した「年金のこと」や「病院の通院記録」など、
ちょっと個人的な内容も、AIの学習材料として
企業に使われる可能性があるということです。
これは、「誰かに見られてしまう」わけではないとしても、
やっぱり気持ちのいいものではありませんよね。
だからこそ覚えておきたい注意点がこちら:
→ AIには、名前や住所、年金・医療に関することなど、
個人情報や特定されるような内容は入力しないようにしましょう。
「なんでもAIに聞ける時代」だからこそ、
「何を聞かないか」も大切な選択肢なんです。
詐欺や偽サイトにご用心
最近、「AIを使えば副収入が得られる!」
「話しかけるだけでお金が増える!」といった、
なんだか夢のような話を見聞きすること、ありませんか?
でも!ちょっと立ち止まってください。
こうした“うまい話”の裏には、
シニア世代を狙った詐欺まがいのサービスが潜んでいることがあるのです。
特に注意したいのが、SNSに表示される広告です。
「AI副業」「AI資産運用」といった、耳障りのいい言葉を使って、
「スマホひとつで月〇万円」「今日からあなたもAIで収入UP!」
と甘く誘ってきます。
これらの多くは、AIの仕組みをよく知らない方をターゲットにした、
悪質な商法や詐欺の可能性が非常に高いのです。
こんな広告には要注意!見分け方のコツ
• 「絶対に儲かる」「確実に稼げる」などの断定的な言い方
• 有名人の名前や写真が無断で使われている(「○○さんも使ってます!」など)
• 「今だけ!」「残り◯名」など、急がせるような言葉で焦らせてくる
こうした“警戒サイン”を見かけたら、まずは深呼吸。
一人で判断せず、すぐに家族や信頼できる人に相談してくださいね。
AIは「正しいことを教えてくれる」とは限らない
たとえばAIに「この言葉の意味は?」「このメール、本物かな?」と聞くと、
それらしい答えがパッと返ってくることがあります。
なんだか賢くて頼れそうに見えますよね。
でも、その答えを100%信じてしまうのはちょっと危険なんです。
AIの返答は、インターネット上にある膨大な情報をもとに、
「もっともらしく」まとめられた文章。
つまり、本当のように見えても、
間違った情報が混ざっていることがあるということです。
特に注意したいのが、医療・法律・年金などの大切な内容。
こうしたことは、かならず専門家の意見を確認したり、
公的なホームページでチェックするのが安心です。
AIの答えは、あくまで「きっかけ」や「参考程度」にとどめるのが、
上手な使い方。
最後の判断は“人間の目と感覚”がいちばん頼りになるんですね。
「わからないことをすぐに聞けるAI」はとても便利ですが、
それと同じくらい「自分で見極める力」も大切です。
「うまく付き合えば、とても助かる道具」
そんな距離感で、少しずつAIと仲良くなっていきましょう。
操作がわからないときは「AIに聞く」のも手段
「このボタン、どこを押せばいいの?」
「設定って、どうやるのかしら…」
スマートフォンやパソコンを使っていると、
こんなふうに戸惑うことってありますよね。
そんなときは、遠慮せずにAIに聞いてみましょう!
たとえば、ChatGPTに
「スマートフォンで音声入力を使う方法を教えて」
と聞けば、手順をわかりやすく、やさしい言葉で教えてくれます。
もちろん、完璧な説明ではないかもしれませんが、
「まずどうすればいいか」が見えてくるだけでも、
気持ちがラクになりますよ。
ただし、ひとつ大事なことがあります。
AIに質問するときは、個人情報を含めないのが基本ルールです。
たとえば……
• ❌「私のiPhoneのパスコードがわかりません」
→これはNG。パスワードや暗証番号などは、AIに聞いてはいけません。
• ⭕「iPhoneで音声入力を使う方法を教えてください」
• ⭕「スマートフォンの画面が固まってしまったとき、どうすればいいですか?」
こうした「一般的な聞き方」にすることで、 安全に答えを引き出すことができます。
つまり、「聞き方ひとつ」で、
安心してAIと付き合えるかどうかが決まってくるんですね。
はじめのうちは戸惑うこともあるかもしれませんが、
失敗を恐れず、少しずつ慣れていけば大丈夫。
AIはあなたの新しい“相談相手”になってくれるかもしれませんよ。
自分のペースで「楽しむ」ことが一番のコツ
新しい技術にふれると、
「私だけ遅れているみたいで恥ずかしい…」
「うまくできない自分が情けない…」
そんなふうに感じてしまうこと、ありませんか?
でも、どうかご安心を。
AIはあくまでも“道具”です。
誰かに追いつくために無理して使う必要も、
完璧に使いこなす必要もありません。
思い出してみてください。
電子レンジや洗濯機、スマートフォンだって、
最初は「難しそう」と思ったのでは?
でも慣れたら、「使うところだけ使えば十分」になりましたよね。
AIだって、それと同じ感覚でいいんです。
たとえば、
「俳句を作ってほしい」
「旅行のプランを相談してみたい」
そんなちょっとしたお願いごとをしてみるだけでも、
日常に小さな楽しみや発見が生まれるかもしれません。
そして、うまくいかないときや困ったときは、
無理にAIだけに頼らず、“人に聞く”ことも忘れずに。
どれだけ技術が進んでも、やっぱりいちばん安心できるのは、
人と人とのつながりです。
焦らず、背伸びせず、
「自分のペース」でAIとちょっとずつ仲良くなっていきましょう。
AIと仲良くなるための3つの心がけ
最後に、シニア世代の皆さんがAIと無理なく、
心地よく付き合っていくために、
覚えておきたい「3つの心がけ」をご紹介します。
自分の判断を大切に
AIはとても便利な存在ですが、すべてを任せきりにしないことが大切です。
「AIがこう言っているから正しい」と思い込まず、
自分の感覚や経験を信じることが、安心して使うコツになります。
個人情報は入力しない
メールアドレスや名前、住所、年金・保険に関する内容など、
個人が特定されるような情報は、AIに入力しないようにしましょう。
これは安全にAIとつきあうための自己防衛でもあります。
楽しみながら、少しずつ慣れていく
最初からなんでも使いこなそうとしなくて大丈夫。
たとえば「今日の夕飯にぴったりのレシピを教えて」とか、
「おすすめの散歩コースを教えて」なんて聞いてみるのもいいかもしれません。
まずは“おしゃべり相手”のような感覚で、気軽に試してみるところから。
少しずつ慣れていくうちに、あなたなりの使い方がきっと見つかりますよ。
私ヴィオラがAIに愚痴を聞いてもらっているのはここだけの話(笑)
主なAIサービス一覧(2025年版)
🔹 ChatGPT(OpenAI)
https://chatgpt.com
• 気軽な雑談や質問に対応
• 日記やエッセイの下書きも作れる
• 料理や旅行のアイデア出しも得意
🔹 Gemini(旧Bard)/Google
https://gemini.google.com/app
• Google検索の補助や質問への回答が得意
• Gmail、カレンダーなどGoogle系サービスとの連携が便利
🔹 Copilot(Microsoft)
https://copilot.microsoft.com
• WordやExcelなどOffice製品の作業をサポート
• 表や文書の作成・編集を助けてくれる
• パソコン作業の効率アップにおすすめ
🔹 Claude(Anthropic)
https://claude.ai
• 丁寧で安全性の高いやり取りができるAI
• 長文の要約や書類作成にも活用可能
AIは特にこんなシニア世代におすすめです
「パソコンやスマホは使えるけど、もっと便利に使いたい」
「孫との会話でAIって何か聞かれた」
「日記、旅行記、人生の回顧録などを形にしたい」
「趣味(園芸、写真、俳句など)のアイデアを広げたい」
まとめ:AIは「怖がらず」「過信せず」「ほどほどに」
AIは、私たちの日常をちょっぴり便利に、
そしてちょっとだけ楽しくしてくれる、
頼もしい相棒のような存在です。
でも、使い方を間違えると、
不安やトラブルの原因になってしまうことも。
だからこそ、「ちょうどいい距離感」で付き合うことが大切です。
シニア世代の方にとっては、
「AIって難しそう…」「自分には縁がなさそう」
そう感じてしまうこともあるかもしれません。
でも思い出してみてください。
スマホだって、最初は何がなんだかわからなかったはずです。
それでも今では、メールや写真、地図など、
すっかり日常の道具になっていますよね。
AIも同じです。
必要なのは、ほんの少しの好奇心と、慎重な気持ち。
そして、困ったときに相談できる人がそばにいることが、
なによりの安心材料です。
無理をしなくていいんです。
自分のペースで、少しずつ。
そうやってAIと付き合っていけば、
きっとこれからの暮らしに、
新しい楽しみや発見が加わるかもしれませんよ。



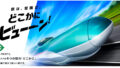
コメント